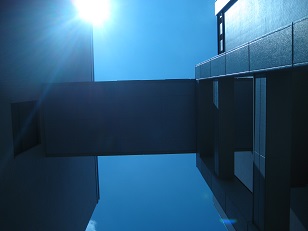暑い夏の 開始を告げる 蝉の声
11 グロー バル化による主体の多元化 (20140731)
消費社会論から自我の多元化を説明することは、しばしば行われるが、もう一つ説得力にかけるような気がする。なぜなら、1980年代のバブルの時代に盛んだった消費社会論が、バブルの崩壊後はあまり活発でないからである。
そこで前々回の話に少し戻らせてほしい。前々回に、冷戦期の自我論を、
①近代的主体
②伝統的日本的自我論
③マルクス主義的主体
に分類した。②と③は共に近代的主体を批判し、主体を他のものとの関係において捉える。②と③の違いは、その「他のもの」の理解の仕方である。
マルクス主義は、「フォイエルバッハ・テーゼ」の第6テーゼにあるように、「人間は社会的諸関係の総体である」と考える。現代では、その「社会的諸関係」は、資本主義的な生産関係という経済関係を中心にしたものとして理解されるだろう。この「社会的諸関係」は、時代、地域によって異なるはずであり、人間のあり方を、具体的に検討するには、社会を特定して議論が必要になる。
伝統的日本的自我論では、その関係は例えば、和辻哲郎の「人間」論のように、あるいは濱口恵俊の「間人主義」のように、人間と人間の関係として考えられるだろう。全ての人間関係は、社会的関係に媒介されているはずであるが、ここでは素朴に人間と人間の関係が考察されているように思われる。その関係は、時代を超えて日本社会に妥当するものとして理解されているのかもしれない。あるいは、それは日本人の間で強く意識化されているが、原理的には日本人の人間関係にかぎらず、人間一般の普遍的な存立構造として理解さているのかもしれない。つまり、時代と社会を超えて、普遍的に成り立つこととして考えられているのかもしれない。
近代的主体に対する批判は、②や③に限るものではない。西洋でも、構造主義による実存主義批判や、共同体論者によるロールズの「負荷なき自我」に対する批判や、ルーマルのシステム論や、ウィトゲンシュタインの私的言語批判や、フーコーの規律訓練型権力に対する批判や、社会構築主義など、多様な批判が行われている。
さらに遡るならば、近代的主体への批判は、フィヒテやヘーゲルの「承認論」に既に始まっているということもできる。これらの批判は、いずれも主体を実体として捉えるのではなく、関係において存立するもの、あるいは関係そのものとして存立するものとして理解する関係主義的な主体理解である。
このような関係主義的な主体理解からの「近代的主体」に対する批判は二種類に分けることができる。一つは、歴史と社会を超えた人間の普遍的なあり方の考察から、近代的主体を批判するもの、もう一つは、論者の生きているある歴史のある社会において「近代的主体」は成立しないという批判である。上に見たように、マルクス主義からの批判の中には、二種類の批判がありうるだろう。日本的な主体理解の立場からの批判も、二種類の批判がありうるだろう。この二つの観点を区別に注意しておくことが明確な議論のためには不可欠である。
関係主義的な主体理解は、近代的実体的個人主義的な主体への批判として登場してきたので、最初にはその批判に重点がおかれるが、その次には、関係の中で主体がどのように成立し構成されているかの説明に重点が移ってくることになるだろう。大庭健の「責任=呼応可能性」の議論はその一つだと言える。(ちなみに、永井均の〈私〉論、および永井均と大庭健の論争は、それ自体大変興味深いし、また戦後自我論において重要な位置を占めるに違いないのだが、それをどのように位置づけたらよいのかは、いまだ思案中である。)
さて、1990年代以
後の「自分探し」ブームの中で登場した新しい概念として、多元主義と物語論という二つの自我論があげられる。もっともこれは日本に限らない世界的な傾向である。そのうちの「多元的な主体」に話しを戻そう。
関係主義的な主体理解を認める時、主体そのものが分裂すること、あるいは多元化するとは、主体を構成する社会的諸関係が分裂すること、あるいは多元化することである。では、主体を構成する社会的諸関係の分裂ないし多元化は、どこにどのように登場しているだろうか。
平野啓一郎が言うように、コミュニケーション手段の多様化、人間関係の複雑化によって、家庭や職場やインターネットサイトやNPOなど様々な社会空間が分裂しており、そのためにある人が演じるキャラが社会空間ごとに異なる。
ただし、それだけでは理由として不十分ではないだろうか。もし国民国家が、究極的にはこれらの社会空間を一つに統合しているのだとすると、それぞれのキャラも一つに統合可能であろう。つまり、社会空間ごとの複数のキャラの使い分けは、一つの人格に属するものとして統合される。フーコーによれば、近代主権国家の規律訓練型権力が、個人の欲望を抑圧するだけでなく、他方で個人の欲望を生産し、欲望の編成によって、近代的主体を生み出したのである。この理解からするならば、主権国家と近代的主体は構造的な補完関係にある。従って、主権国家は、個人を構成する社会的諸関係、諸空間を編成しているのであり、それらは主権国家によって統合される。
(注、ドゥルーズがいうように、「規律社会」から「管理社会」への変化が20世紀初頭に起こっているのだとしても、主権国家が存続する限り、それが社会的諸関係を管理統合するだろう。ちなみに、この「管理社会」は、第一次大戦頃から登場すると言われる「総力戦体制」に対応するのかもしれない。)
(注、私は書庫「問答としての経済」で述べたように、近代的「個人」は資本主義経済の中で誕生したと考えるが、近代主権国家(近代的主体)と資本主義社会(近代的個人)の関係の考察は、今後の重要な課題である。)
しかし、グローバル化のなかで、主体を構成する社会関係が国民国家を越えてグローバルに広がっているのだとすると、それらの社会関係を国民国家が統合することはできない。したがって、主体を一つに統合するものはなくなる。主体を構成する社会的諸関係の多様化が、原理的に国民国家の中に収まらなくってきていることが、主体の多元化を引き起こしているのではないだろうか。グローバル化における人、物、金、情報の国境を得た移動が、私たちを構成する社会的諸関係を国民国家で統合できないものにしている。
(注、それを歓迎しないものは、ナショナリズムを復活させようとする。しかし、人々が好むと好まざるに関わらず、どうやら経済のグローバル化は不可避的に進んでゆく(右翼政権ですら、TPPを推進する。なぜなら経済の国家間競争に勝つためにそれが必要だからである)。つまり、好むと好まざるに関わらず、主体の多元化は不可避的に進んでいくだろう。それに反応して、ナショナリズムは執拗にバックラッシュする。国家というシステムをナショナリストに委ねてしまうことは非常に危険である。それを避けるには、グローバル化の進展の中に、過渡的であれ、国家システムを適切に再設定する必要がある。グローバル化の中で、国家に求められるのは、国内的および国際的な再分配機能ではないだろうか。
安倍政権は、一方では、TPPを推進し、法人税をさげ、グローバル化に棹さしており、他方では、国内の再分配は消費税で行おうとするので余計に格差を拡大し、その不満をナショナリズムにむけ、「いつでも戦争できる国家」(総動員体制)を作ることによって、主権国家を維持しようとしている。)