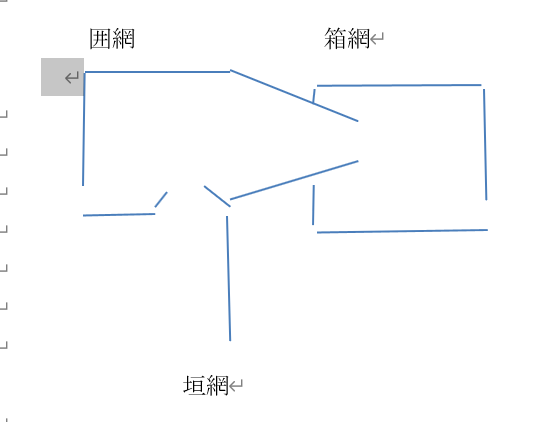[カテゴリー:人はなぜ問うのか?]
バレットは、「内因性脳活動」ないし「内因性ネットワーク」は、人が生きているか限り、絶えず膨大な予測をしていると考えている。彼女はそれの証拠をあげておらず、第4章の注15でAndy Clark, Jakob Hohwy, Sophie Deneve and Renard Jardri,Andyの文献を挙げているだけである。そこで、Andy Clarkの論文 ” What ever Next? Predictve Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science,” 2013と彼の近作Searching Uncertainty、2016とJakob Hohwy, The Predictive Mind, 2013をつまみ読みしてみた。
ClarkとHohwyの研究関心は大変にている。どちらも情動研究よりは認知研究に重心がありますが、ともに面白い。彼らは、人間の認知プロセスを説明するときに、ディープラーニングの研究を応用してアプローチする。予測をしてそれをチェックしてエラーを修正し、次第にエラーを少なくしていくというディープラーニングの手法を人間に当てはめて、人間の知覚を説明しようとする。
(認知や情動を理解するには、やはりディープラーニングのプログラムを勉強することが必要なようだ。)
(ちなみに、彼らはともに、Helmholtzの視覚生理学の研究を、その先駆として高く評価している。ヘルムホルツは、Handbuchder Physiologischen Optikの第三巻で「知覚のための無意識の推論」を無視式的な知覚的推論」の重要性をしてしていたようで、それを高く評価する。 HohwyのPredictive Mind (p.5)によれば、Helmholtzのこの研究はカントの認識論の影響を受けているとのことである。)
今後は、探索と発見の関係(広義での「探索と発見」)を、それが言語によって行われるときには、「問いと答え」と呼び、言語に寄らない場合には、「探索と発見」(狭義での「探索と発見」)と呼ぶことにしたい。人間以外の動物、および言語を獲得する以前の人間については、探索と発見として語り、言語を獲得した後の人間については問答として語ることになる。ただし、言語を獲得した後の人間も、言語を用いないレベルで探索と発見をしている場合があるだろう。
ところで、「予測」は、探索による発見として、あるいは問いに対する答えとして得られるものだろう。なんの必要も理由もないところで、いきなり何かが予測されるということはありえず、何かについての何かの予測が生じるとしたらそれが求めらているからであろう。
「予測」についても、それが探索による発見として得られる場合と、問いに対する答えとして得られる場合があるを区別できるだろう。そして、この区別とは別に、「予測」についても、「意識された予測」と「無意識の予測」を区別できるだろう。
前に「27 意識的問いと無意識的問い (20210120)」で「問いを意識するの」場合と、「問いの答えを意識する場合」についてのべた(そこでは、証明はなく、結論だけを述べたのだが、それはどうやって証明したらよいのかわからなかったからである。しかし「より良い対案」を今のところ思いつかない)。後者、つまり問いの答えを意識する場合には、次の3つであった。
①意識的に立てた問いの答えを得たときには、私たちは、その答えを常に意識している。
②無意識的に立てた問いの答えを得たときには、大抵は、それを意識しない。
③しかし、その答えが、他の意識している命題と衝突するとき、私たちは、その答えを意識するだろう。
これを「予測」に当てはめると次のようになる。
①意識的におこなう探索にたいする(発見としての)予測を得たときには、私たちは、その予測を常に意識している。
②無意識的におこなう探索にたいする予測を得たときには、大抵は、それを意識していない。
③その予測が、他の意識している予測と衝突するとき、私たちは、その答えを意識するだろう。
では、無意識の予測が、他の無意識の予測と衝突するときには、どうなるだろうか。
その場合には、それをどう解決するかは、無意識の探索になるのではないだろうか。
ところで、ディープラーニングによるコンピュータの探索は、意識を持たないので、その成果である予測も意識を持たない。上の①にあるように、予測が意識的なものになるのは、意識的な問いに対する答えとして生じる時だとすると、意識の発生を説明するには、意識的な探索がどのように生じるのかを説明する必要がある。
話があちこちしてしまいましたが、いろいろと考えるべきことが分かってきました。しかし、とりあえずバレットの情動の説明にもどって、最後まで見ることにしたいとおもいます。