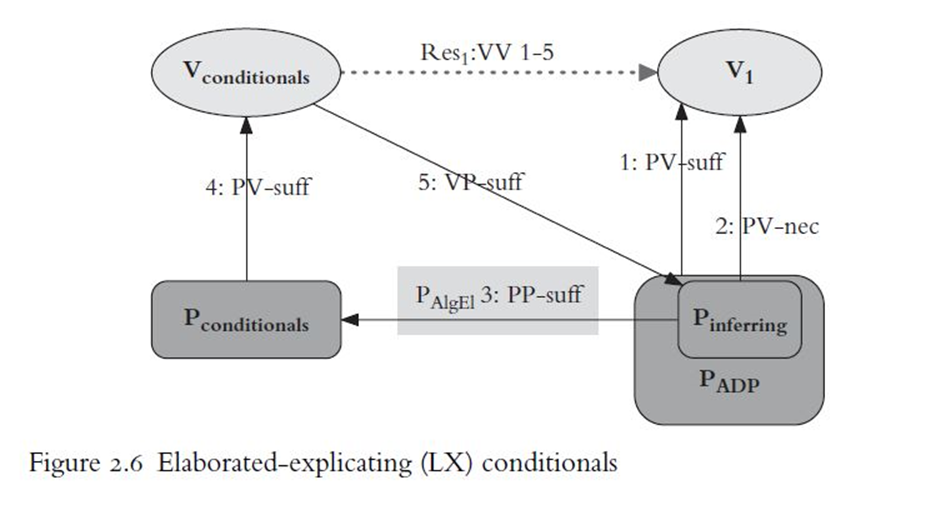[カテゴリー:問答の観点からの認識]
前回述べたように、ブランダムは、主張やコミットメントの両立不可能性は、対象や主体が一つであることを前提して生じていること、また、それらの両立不可能性を修復するプロセスは、対象や主体の統一性を確立するプロセスでもあることを、主張します。
(これによって、対象に関する事実の客観性を証明できているとは言えないと思いますが、ブランダムならば、対象は客観的に然々である、と語ることは、of志向性で語るしかなく、これ以外の仕方で対象の客観性について語ることはできないと言うでしょう。だからこそ、ブランダムは「概念的観念論を最終的に主張するのです。」
主張やコミットメントの両立不可能性が成立するのは、対象や主体が一つであるためである>というブランダムの指摘に対しては、問答の観点から次の批判が可能です。
#コリングウッドの指摘からの展開(2023年3月10日の研究会での発表原稿の一部です)
コリングウッドの指摘によれば、二つの命題が矛盾するのは、それらが同じ問いに対する答えであることによる。これに従うならば、二つの概念関係が両立不可能であるのは、二つの概念関係が同じ対象についてのものであるからではなく、同じ問いに対する答えであるからである。なぜなら、同じ対象であっても、問いが異なれば、答えが異なっていても、両立不可能ではないからである。たとえば、「リコリスはおいしい」と「リコリスはまずい」はそれぞれの相関質問が「チョコレートを食べたあとリコリスを食べると、リコリスはおいしいですか」と、「リンゴを食べた後リコリスを食べると、リコリスはおいしいですか」とであるとき、この二つの答えは両立可能であるかもしれない。
ここで次の反論があるかもしれない。この場合、<「チョコレートを食べた後のリコリス」と「リンゴを食べた後のリコリス」は同一の対象ではないので、二つの答えが両立可能になるのだ>という反論があるかもしれない。この反論をみとめてもよいのだが、しかしこのように考えるときには、対象が同一であるかどうかは、問いが同一であるかどうかに依存することになる。
したがって、主張が両立不可能であることは、問いの同一性を前提としていることになり、問いの同一性を構成することになる。コリングウッドがいうように、二つの命題が両立不可能であるのは、それらの相関質問が同じであることによる。
同様のことは、コミットメント両立不可能性についても言えるだろう。二つのコミットメントが両立不可能であるのは、それが同一の問いに対する答えであることによるのであり、同一の主体のコミットメントであることによるのではない。「コーヒーが欲しいですか」という問いに、「欲しいです」と答えることと「欲しくありません」と答えることが両立しないのは、主体が同一だからではなく、問いが同一だからである。同じ主体であっても、異なる状況で発せられたのであれば、同じ疑問文でも異なる意味をもつ問いとなる。
複数の主張やコミットメントが両立不可能になるのは、たしかにそれらが一つの対象、一つの主体についてのものであることが必要だが、しかしそれではまだ十分ではない。それらが同一の問いに対する答えであることが必要である。(つまり、問いの同一性が、対象や主体の同一性を構成するのである。)
―――――――ここまで
ハイデガーは、『存在と時間』の第二節で、問いが次のような3つの要素からなると考えました。
・問われるもの(Gefragtes)
・問い合わされるもの(Befragtes)
・問い求められること(Erfragtes)
ある対象についての問いに答えるには、何かに何かに問い合わせることが必要です。推論で問いの答えを得るときには、他の知識に問い合わせて、それを推論の前提として使用します。推論によらずに直接に答えをえるときには、例えば、知覚報告で答えると時には、知覚に問い合わせて、知覚報告を得ることになります。推論の前提となる知識は、別の問いの答えとして得られると思われます。では、知覚に問い合わせて、知覚報告を得ることは、どのようにして可能なのでしょうか。
これについて、次に考えたいと思います。
。