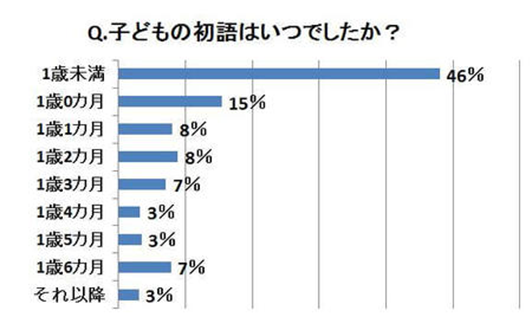[カテゴリー:人はなぜ問うのか?]
前回の最後に次のように書きました。
「<ある事実に注意してほしい>という意図を他者に伝達しようとする意図(伝達意図)は、<ある事実に注意している>という状態を、他者と共有することを目指しています。つまり、共同注意を目指している意図だと思われます。そうだとすると、伝達意図は、(他の対象でも同じ対象でもよいのですが)ある対象への共同注意の経験を前提します。」
ここでは、「伝達意図」と「共同注意」の関係について、もう少し詳しく考えたいと思います。
二人の人間AとBがいて、Aが、Bが対象Oに注意することを意図1し、Aがその意図1をBに伝達しようと意図2するとします。この意図2のような意図を「伝達意図」と呼ぶことにします。
またAとBが対象Oに「共同注意」とは、<AとBがともに対象Oに注意し、かつ両者がそのことに気づいている>ということだとします。では「伝達意図」と「共同注意」はどのように関係するでしょうか。
この二つの関係としては、次の二通りが考えられます。
1,Aが対象Oに注意し、それをBに伝えようとする伝達意図によって、共同注意が成立する。
(ちなみに、Aが伝達意図をもつことは、さまざまな目的を持ちえます。つまり、伝達意図の実現によって共同注意が成立するとしても、そのことは、伝達意図がもちうる目的の一つに過ぎません。伝達意図が実現しても、共同注意が成立しないこともありえます。例えば、教師が複数の生徒に、顕微鏡の中の細胞を見てくださいと言い、一人の生徒がそれを見る前に、隣の生徒に同じように顕微鏡の中の細胞を見て下さいと言う場合です。また、かりに共同注意が成立したとしても、それは目的ではなく、他のことが目的であり、共同注意は付帯的に成立するにすぎないこともありえます。例えば、教師が生徒にあの星を見て、あの星の名前を考えてくださいという場合、生徒と教師がその星にともに注意するとしても、そのことは、この場合の伝達意図の目的ではありません。)
2,AやBが個別に対象Oに注意する前に、したがって個人が対象Oへの注意を伝えようとする伝達意図の成立する前に、AとBの対象Oへの共同注意が成立し、その後に各人の対象Oへの注意が成立する。
幼児の発達過程において、伝達意図も共同注意もできるようになっているとすると、その場合には、上記の1のケースがあるでしょうが、発達過程において、共同注意が最初に成立するときには、上記の2のケースになると思われます。その根拠は、指示行為が、共同注意の後に発生するということです。幼児の発達においては、伝達意図よりも、共同注意の成立が先行するようです。トマセロによると、共同注意は、9か月ころ成立し(これがトマセロの「9か月革命」です)、指さしの成立は、トマセロによれば11か月ころ、アダムソンによれば12か月ころ(cf. ローレン・B・アダムソン著『乳児のコミュニケーション発達』(大藪秦・田中みどり訳、川島書店、p.21)のようです。指さしは、他者の注意をある対象に向けようとする伝達意図にもとづく行為ですから、伝達意図の成立は、共同注意の成立の後になります。
では、対象への幼児の注意と、対象への幼児と大人の共同注意は、どちらが早く成立するのでしょうか。私には確証と言えるものがまだ見つからないのですが、共同注意が個人の注意に先立つと予想します。アダムソンが引用しているヴィゴツキーの次の言葉を孫引きしておきたいと思います。
「子供の文化的発達に見られる機能はすべて2回出現する。最初は社会的レヴェルで、その次に個人的レヴェルで。最初は人と人との〈間で〉(精神間)、その次に子どもの〈内部で〉(精神内)。」(同上p.38からの孫引き)
(カテゴリー【共同注意と指示】では、
・個人的な注意よりも、共同注意が発達上先行するということ、
・個人による指示よりも、「共同指示」ともよぶべきものが、発達上先行すること、
トマセロの「シミュレーション理論」を批判して、この二点を証明しようしました。トマセロ、アダムソン、大藪の議論を紹介しつつ、考察しましたが、上記の証明としては、不十分なままに、中断しています。それを書いていたのは2008年で、その時私は、ミラーニューロンや能動的推論や予測誤差最小化メカニズムについて知りませんでしたが、今ならそれを考慮してもう少し進んだ議論ができそうな気がします。)
#共同注意は、予測モデルとして成立するのではないでしょうか。
<私は、自分と他者が同じ対象Oについて一緒に共同注意しているというモデルから、自分と他者の対象についての注意の内容を推論する。他者が現実に注意を向ける対象が、私が予測する対象とは異なっているならば、私は当初のモデルを修正する、この新しいモデルから…>という予測誤差最小化メカニズムによって/として成立するのではないでしょうか。共有注意は、<あることを予測し、それから予測する帰結を、現実と比較して、誤差が最小化するように、予測を修正する>という予測誤差最小化メカニズムによって/として成立する。
#共有知は予測誤差最小化メカニズムによって/として成立する
共有知とは、「AもBもpを知っており、そのことをAもBも知っており、そのことを・・・(以下無限に続きうる)」というような知ですが、これは正確な定式化ではありません。実は、それを適切に定式化することは非常に困難です。そこからわかることは、共有知を個人知から構成することはできないということです。では、共有知は存在しないのか、といえば、そうもいきません。なぜなら、私たち他者とコミュニケーションするときには、共有知を想定しているからです。以下は、カテゴリー「世にも不思議な共有知」に書くべきことなのですが、そこには、改めて書き込むことにして、今回思いついた、この問題の解決方法を伝えたいと思います。
それは、<共有知は、予測モデルとして存在しているのではないか>ということです。
共有知は、<共有知というモデルから、私は、自分と他者が同じ知をもっていることを推論する。他者が現実に持つ知がそれと異なることが分かったら、私はモデルを修正して、修正された共有知が共通であることを予測する>という予測誤差最小化メカニズムによって/として成立するのではないでしょうか。
「共同注意」と「共有知」についてのこれらの定式では、それらは、個人が行う予測誤差最小化メカニズムであって、共同で行う予測誤差最小化メカニズムではありません。したがって、これではこれらの説明としては、まだ不十分かもしれません。また、これらの定式化における「予測誤差最小化メカニズム」は、無意識的なものなのか、意識的意図的なものなのか、という問題もあります。
ここでは、言語的探索である<問うこと>がどのようにして生じるのか、そして目下の文脈では、それを予測誤差最小化メカニズムとして説明することです。そのために、共同注意や共有知を予測誤差最小化メカニズムとして説明しようとしています。共有知を予測誤差最小化メカニズムで説明できるのかどうか、さらに考察したいと思いますが、今年はこれで最後になりそうです。
皆様良い年をお迎えください!